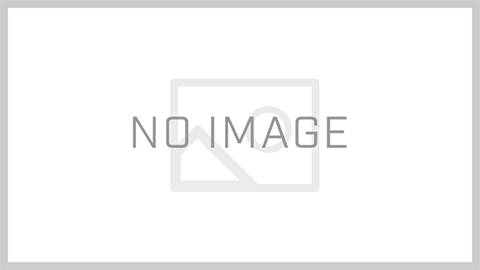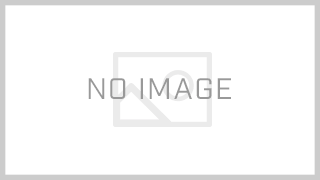先日スーパーへ買い物に出かけた時のことです。
うっかりスマホを置き忘れてきたことに、店に着いてから気がつきました。
「あっ、スマホ忘れた!」と思った瞬間から、焦りや困惑など、いわゆる「パニクった」状態になった自分に、「私スマホにすごく依存している」と自覚しましたね。
実は私がスマホに買い替えたのはほんの数年前。
周囲の人たちのほとんどがすでにスマホ持ちになっていた頃まで、「二つ折りで十分だよ」と言っていた人でした。
そんな私でも、いざスマホを使い始めるとその便利さにすぐ夢中になり、今では手放すことのできないアイテムになっています。
そして今、「スマホ認知症」というワードが注目を浴びるようになってきました。
「スマホ依存」という言葉は聞いたことがありましたけれども、「スマホ認知症」とは?
これは、主にスマホを多用する30代~50代以下の世代で、心身に不調をきたす人が増えている状況の中、そういう人たちに見られる「認知症に似た症状」のことを指すものだそうです。
具体的には、「人や物の名前がすぐに出てこない」「簡単な計算ができなくなった」などのような、通常アルツハイマー型認知症患者に見られるような「深刻な物忘れ」の症状です。
アルツハイマー型認知症の場合、MRIで検査をすると脳に萎縮などの異常が見られるのですが、「スマホ認知症」の疑いがある患者の場合は、同様の検査をしても脳自体に異常は見られません。
脳神経外科医の奥村歩氏によれば、こうした症状の原因として考えられるのは、「スマホ依存による『脳過労』」だそうです。
奥村医師は「脳は入ってきた情報を整理整頓し、記憶の棚から出力している。だが情報過多でその機能が追いつかなくなると、必要な情報をうまく取り出せなくなり、『ど忘れ』や『うっかりミス』といった『スマホ依存症』とも言える症状が現れる」と話します。
スマホ認知症に陥ると、「最近料理が手際よく作れなくなった」というような、段取りや計画に沿って物事を進める「遂行実行機能」が低下し、コミュニケーション能力や企画力・創造力の低下なども表れるそうです。
これと連動して、心身の状態をコントロールしている前頭葉の機能低下も起きるとされ、手足の痛み、動悸、めまいなどさまざまな体調不良にもつながることもあるそうなので、こうなってくると、「スマホないと困るから~」などと呑気に済ませることはできなくなりますね。
最も問題なのは、このような状態を放置しておくと、将来的に本当の認知症になるリスクが高くなるということ。
それを防ぐためには、「スマホから距離を置き、『ぼんやりする時間』を意識的に作ること」が大切だと言います。
そうすることで、頭の中の情報が整理され、脳機能の回復につながるそうです。
また、一定のリズムで体を動かすことも脳機能の活性化に役立そうで、具体的には、散歩や自転車に乗るといった軽い運動のほか、料理や皿洗いといった家事仕事をすることも有効とのことです。
私も含め、最近スマホに依存気味という自覚のある方は、ぜひ日常生活の中にスマホから離れる時間を作ってみてはいかがでしょうか。