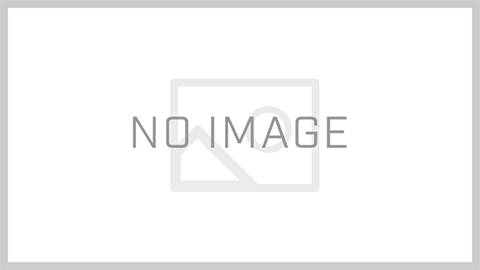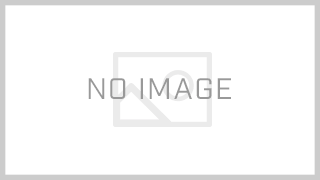「大寒」を過ぎて、厳しい寒さが続く中にも、日差しに少しづつ力強さを感じるようになってきました。
2月は1年で最も寒い季節。
でも、陽光だけは一足先に「光の春」となって、私たちに来たるべき春の訪れを予感させてくれます。
そんな光のシャワーが窓ガラス越しに降り注がれる中、今日もこうして1日のスタートを切れることに感謝しながら、いつものようにネットをのぞいて見ると・・・
ん?トレンドワードの中に「ライバルが手を結ぶ日」というのがある。
これってどんないわれがあるんだろう、そしてなぜ今日・1月21日が「ライバルが手を結ぶ日」なんだろう。
気になって調べてみました。
調べてみるとこの日の制定には、いわゆる「幕末好き」「明治維新好き」にとって興味深いいわれがあったんですね。
時は幕末、1866年(慶応2年)のこの日、薩摩藩の西郷隆盛と小松帯刀、長州藩の桂小五郎(後の木戸孝充)らが、土佐藩の坂本龍馬らの仲介で京都で会見、薩長同盟を結んだ・・・ということにちなんだそうで、1月21日が「ライバルが手を結ぶ日」となったとのことです。
この辺りの政治的な駆け引きのあれこれについては、これまで様々な映画やドラマの中で、それこそありとあらゆる角度から描かれてきていて、見る人の視点の置き方によっても、様々な見方ができる、面白い歴史的な出来事だと個人的に思っています。
シンプルにまとめるなら、その当時「公武合体」という立場から幕府の開国路線を支持しながら幕府改革を求めた薩摩藩に対し、急進的な攘夷論で反幕府的姿勢を強めていた長州藩という、当時幕末政治において二大勢力であり、しかもお互いに相容れなかった両藩が、「倒幕」というひとつの目的のために「ライバル」でありながらも手を組み、それが結果的に2年後の「明治維新」につながったということです(あ、全然シンプルじゃなかったかw)
この「薩長同盟」の仲立ちをした坂本龍馬のことは、特に歴史に興味がない人にも、多分有名なはず。
今朝からネット上が「#ライバルが手を結ぶ日」で大にぎわいな様子を見るにつけ、新しもの好きだった龍馬がもしこの様子を見ていたら、さぞかし面白がっただろうなぁ~などと、思わずにやにやしてしまいました。