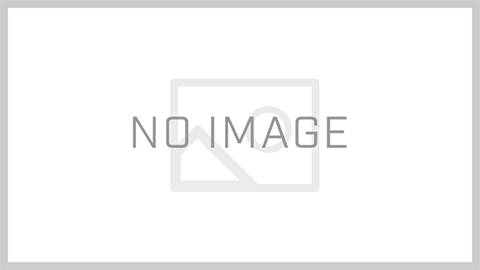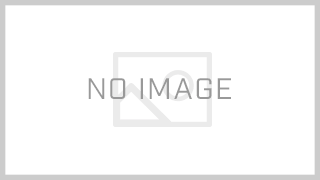10月18日、イスラエル北部沿岸の海底で、今から約900年前の十字軍騎士が使っていたと思われる剣が見つかったそうです。
あるスキューバダイバーが見つけたものだそうで、剣の刃渡りは約91㎝、柄(つか)の長さは30㎝に上り、海洋生物に覆われた状態で発見されたものの、これほど保存状態が良いものはまれだとのこと。
考古学的見地からすると、これは大発見ではないでしょうか。
そもそも「十字軍」とは何か。
高校時代に世界史で学んだ時の知識がおぼろげにあるだけなので、いまいちど調べ直してみました。
「十字軍」とは、中世ヨーロッパのカトリック諸国が、聖地エルサレムをイスラム教諸国から奪回することを目的に派遣した遠征軍のことを言うそうです。
始まりは1096年から1099年までと言われており、この結果シリアからパレスチナにかけての地中海東岸には、エルサレム王国を筆頭とするいくつかの十字軍国家が作られました。
その後も十字軍は何度も遠征を繰り返していきますが、次第に十字軍国家は衰えていき、1271年から翌年にかけて行われた第九回十字軍(※第八回とみなされることもあるそうです)を最後に、十字軍国家は消滅。
十字軍当初の目的であった「聖地エルサレムの奪還」という目的が達成されていた期間は、1099年から1187年、および1229年から1244年ということになるそうです。
時代があまりにも遠すぎて、正直「ゲームの中のストーリーみたい」と感じなくもありませんが、エルサレムを巡るキリスト教徒とイスラム教徒の宗教上の対立が今なお続いていることを思うと、実に根の深い問題なのだなぁと驚かされます。
そして、その十字軍に参加したと思われる騎士の剣がイスラエルの海の底深くに今まで眠っていたとは。
海の底から引き上げられた剣を持つ考古学者、コビー・シャルビット氏の写真が今朝のネットニュースに掲載されていましたが、びっしりと貝などがついた状態ではあっても、一目で西欧の騎士が持つ剣とわかる美しい形を保っていました。
イスラエル考古学庁は、この剣を洗浄し、分析した後一般公開するそうです。