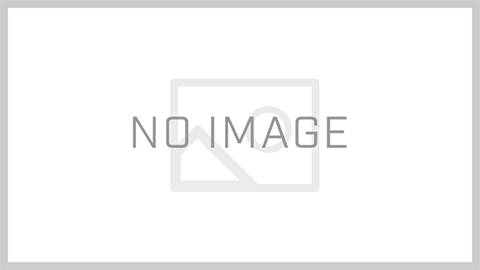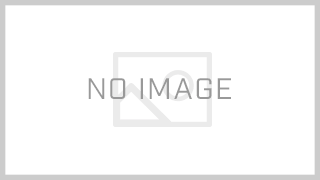れっきとした学術的大発見なのに、なぜかほっこりするニュースが今朝各メディアで伝えられました。
それは、鹿児島大学が発見したある「甲殻類」の話題です。
この甲殻類は、鹿児島県出水市の干潟で採取された、ハゼの仲間(チワラスボ)の尾びれに付着していた体長約1.3㎜あまりの生物。
昨年5月に発見されたこの甲殻類は、小さな茶色の体に甲羅を持ち、動物プランクトンを含む「カイアシ類」のグループに分類されると考えられていますが、鹿児島大学の上野大輔准教授によると、この甲殻類の顎などが他にない独特の形をしていることから、「新しい科の新種」と結論づけたそうです。
学名は「コレフトリア・シラヌイ」、これはギリシャ語で「ダンサー」を意味するワードだそうです。
そして和名については、この甲殻類が顎を使ってハゼの尻びれにかじりつくような姿から、「NHKみんなのうた」の人気キャラクター「おしりかじり虫」にちなみ、「オシリカジリムシ科」の「オシリカジリムシ」と命名したとのことです。
「おしりかじり虫」!これとっても懐かしい!
ボイスチェンジャーを通した声で「おしりかじりむし~~~♪」と歌うこの歌が初めてテレビで流れたのは、2007年のことでした。
その頃まだ小学生だった長男と一緒に、よく口ずさんだことを思い出します。
そんなユーモラスな歌の主人公(?)の名前を、新発見された生物につけるセンスがとっても素敵!
上野准教授は、「親しんでもらえるような名前にしたいと思ったのがきっかけです。魚にしがみつき、表面の何かを食べていたのではないか」と語られているそうです。
また、「おしりかじり虫」の作者・うるまでびるさんは、今回のことに関して「「僕らが作った架空のキャラクターが本物になったと思い、びっくりしました。学術的な名前として世の中に残るのはうれしいです。」というコメントをされています。